
シミ取り ボトックス レーザーフェイシャル 化粧水 占い 星座占い 痩身 美容外科ランキング 美容整形 美容整形体験談 美容整形外科比較 韓国美容整形外科
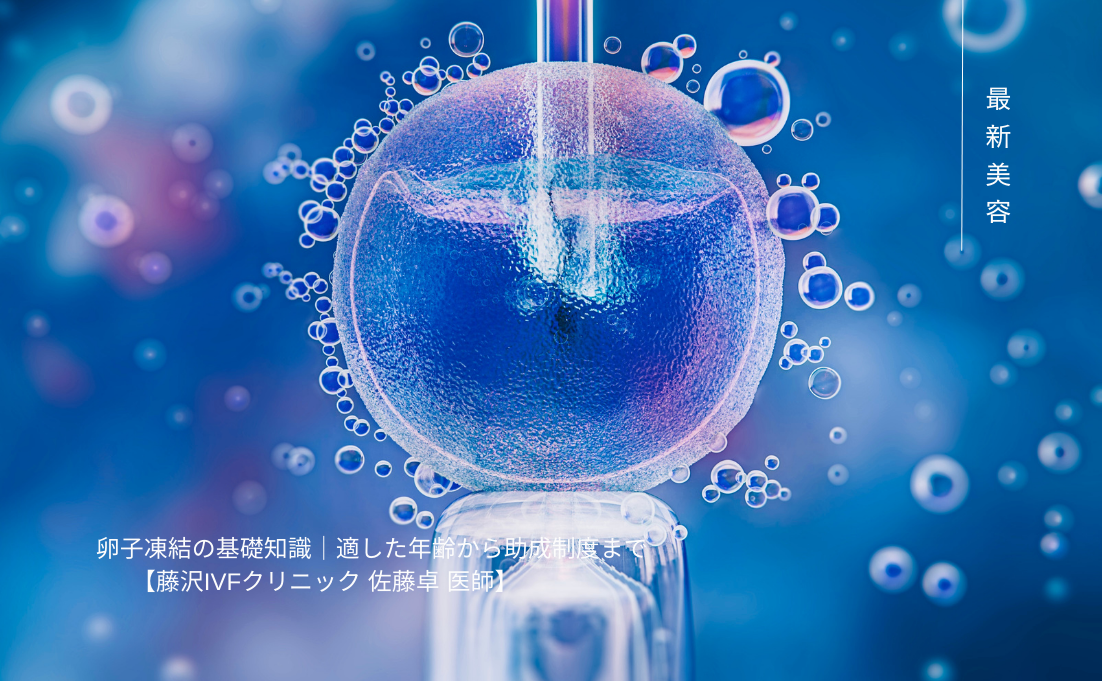
近年、キャリアやライフプランの多様化に伴い、「卵子凍結」に注目が集まっています。
将来の妊娠に備えて卵子を保存しておくことで、人生設計の選択肢を広げられると考える女性が増えているのです。
一方で、がん治療に先立って卵子を保存するなど、医療的に必要とされるケースもあります。
しかし、「実際の流れはどうなっているの?」「成功率やリスクは?」「費用はどのくらいかかるの?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。
そこで今回は藤沢IVFクリニックの佐藤 卓医師に、卵子凍結の現状や特徴、安全性、費用、助成制度などについて詳しく伺いました。
卵子凍結を検討している方にとって、信頼できる判断材料となる情報をお届けします。
卵子凍結は、将来の妊娠に備えて卵子を採取し、「ガラス化凍結法」という技術で凍結・保存する医療行為です。
最近では、キャリア形成やライフプランの選択に備える「社会的適応」として実施するケースが増えています。
一方で、がん治療前後の患者さんに対しても重要な役割を担う存在です。
抗がん剤や放射線治療によって卵巣機能が低下し、妊娠の可能性が損なわれる場合があるため、その前に卵子を保存しておく「医学的適応」の卵子凍結も行われています。
医学的適応としての卵子凍結では、近年は自治体による助成制度が広がりつつあり、卵子凍結を検討する際の後押しになっています。

藤沢IVFクリニックでは、がん治療に関連した「生殖医療」としての卵子凍結にも対応しており、必要な施設認可申請をクリアした体制を整えています。
医学的適応だけでなく、社会的な目的で卵子凍結を希望する患者にも幅広く対応している点が強みです。
同院の特徴は、患者一人ひとりのライフプランに寄り添ったカウンセリングを重視しているところです。特に働く女性が通いやすいように配慮し、ホルモン療法を駆使することにより、治療が仕事や日常生活に支障をきたさないよう調整しています。
また、安全性と成果の両立を大切にしています。卵巣過剰刺激症候群(OHSS)などの合併症を予防しつつ、できる限り多く、質の良い卵子を確保できるよう細心の注意を払いながら治療を行っているのが魅力です。
安全性に偏りすぎることなく、将来の妊娠・出産につながる満足度の高い結果を目指す姿勢が強みとなっています。
卵子は、多く採取できれば将来的に妊娠の可能性が高まると考えられています。しかし、採卵数は安全性とのバランスを考えることが重要です。
例えば、一度に多く採卵すると「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」のリスクが高まり、血栓症や体調悪化を招く恐れがあります。そのため、患者が希望する数が30個であっても、安全面から15個程度に抑え、複数回に分けて採卵することもあります。
さらに、卵子を多く保存するほど保管費用の負担も増えます。予算やライフプランに応じて、無理のない数を検討することも重要です。
実際には、卵巣の反応や体質によって採れる数は人それぞれ異なります。藤沢IVFクリニックでは、医師の経験と知識をもとに安全性と希望の両立を図りながら、最適なバランスを提案しています。
卵子は年齢が上がるにつれて数も質も低下し、妊娠率に大きく影響するものです。そのため、卵子凍結は若ければ若いほど有利とされています。
参考文献のデータによると、34歳で20個の卵子を凍結すれば将来的な出産率は約90%、37歳では同じ20個で約75%、42歳では約37%に下がると報告されています※1。このように、年齢によって結果が大きく変わるのです。
ただし、費用の問題から若い女性ほど実施の決断が難しい現実もあります。そのため、持病やライフプラン、経済的な状況を含めて、最適なタイミングを医師と相談しながら検討することが大切です。
※1 Goldman RH, Racowsky C, Farland LV, Munné S, Ribustello L, Fox JH. Predicting the likelihood of live birth for elective oocyte cryopreservation: a counseling tool for physicians and patients. Hum Reprod. 2017;32(4):853–859.
卵子凍結を検討する際は、まずクリニックでの相談から始まります。最初の段階では、必ずしもすぐに実施を決めなくても構いません。
カウンセリングでは、血液検査によって卵巣の予備能を示す「AMH値」などを確認し、自分がどのくらい卵子を確保できる可能性があるのかを把握します。そのうえで、医師と一緒に実施するかどうかを判断していきます。
クリニックによって安全性や成績を重視するバランスが異なるため、複数の施設で話を聞いたうえで、自分に合った環境を選ぶ女性も少なくありません。
相談を重ねることで、不安や疑問を解消しながら意思決定を進められるのが特徴です。

卵子凍結の成功率に大きく影響するのは、先ほどもお伝えしたとおり「卵子を凍結した年齢」です。年齢が若いほど卵子の質が良く、解凍後の生存率や妊娠率も高くなります。
もう一つの要素は「卵子の数」です。多く凍結できるほど妊娠の可能性は高まりますが、年齢と組み合わせて考えることが重要です。
技術面では、従来の「スローフリーズ法」では細胞内に氷の結晶ができやすく成績が安定しませんでしたが、現在主流の「ガラス化凍結法」によって卵子の損傷リスクが大幅に低下し、実用性が飛躍的に向上しました。
それでも最終的な成功率を決める最大の要因は、凍結時の年齢と確保できた卵子の数であると佐藤医師は強調されています。※2
卵子凍結における採卵は、日帰りで行える比較的安全な手術です。経膣超音波下で細い針を用いて卵子を採取し、麻酔を併用することで安心して受けられる体制が整っています。
ただし、リスクが全くないわけではありません。まれに感染症や出血の可能性はあるものの、頻度は低いとされています。
より注意が必要なのは「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」です。ホルモン刺激によって卵巣が腫れ、腹水の貯留や血栓症を引き起こす危険性があります。場合によっては採卵数を意図的に減らしてでも安全性を優先する判断が求められます。
予防法はいくつも存在し、重症化を避けるための対策がとられていますが、絶対的に防げる方法はありません。そのため、患者のライフスタイルや治療背景をふまえ、個別に安全性と効果のバランスを考えた診療が行われています。
卵子の保存期間については、論理的には「半永久的に保存できる」と考えられています。
ただし、保存している間に卵子の質が良くなることはなく、わずかながら劣化の可能性はあります。
現在主流の「ガラス化凍結法」では、その変化が非常に緩やかで、10年後や20年後に使用しても妊娠を期待できる水準を保てると考えられています。
重要なのは保存年数よりも、凍結した時点での年齢です。
40歳を超えてから凍結を試みる場合は、子どもを1人妊娠・出産するためには複数回の採卵が必要になることもあります。
保管方法については、液体窒素を用いた特殊なタンクで保存するのが一般的です。
最近では、専門の保管業者に委託するケースも増えています。
卵子を長期保存する際には、クリニックだけでなく専門の保管業者に委託するケースもあり、標準化された環境で長期保存が可能です。
選び方の基準として、まず「多くのクリニックが提携している業者かどうか」も一つの目安になるでしょう。
実績のある業者であれば、患者にとっても安心感につながります。
保管業者の中には、全国どこで採卵しても中央施設で管理し、将来別のクリニックで体外受精を行う際には移送まで担うサービスを提供しており、安心感を高めています。
採卵した場所とは別の地域のクリニックで体外受精を希望する場合、業者が卵子の移送をサポートしてくれる仕組みがあれば心強い選択肢となります。
もちろん、クリニック内での保存でも問題はありませんが、費用やサービス内容を含めて比較し、自分に合った保管先を選ぶのがおすすめです。
卵子凍結の費用は、主に採取できる卵子の数と使用するホルモン剤の種類によって変動します。
卵子を多く採取できれば必要な医療資材も増えるため、費用が高くなる傾向があります。
ホルモン剤については、従来型の比較的安価な薬剤から、ペン型で扱いやすくアレルギー反応も起こりにくい高価な薬剤まで幅広くあり、選択によって5万〜10万円ほどの差が出ることも。
ペン型で扱いやすく、「かゆみ」や「発赤」といったアレルギーに似た症状も起こりにくい高価な薬剤まで幅広くあり、1回の採卵周期で10〜15個の卵子が取れた場合、総額はおおむね40万〜50万円程度となるケースが多いです。
なお、がん治療に伴う医学的適応の卵子凍結については、全国的に助成制度が整備されている一方で、キャリアやライフプランを理由とした社会的適応の場合は、東京都を除き助成制度がまだ整っていないのが現状です。
卵子凍結に関する助成制度は、目的によって大きく異なります。
がん治療に伴う「医学的適応」の卵子凍結については、全国的に助成制度が整備されており、多くの自治体でサポートを受けられる状況です。
抗がん剤や放射線治療によって妊娠の可能性が下がる前に卵子を保存する取り組みを支える仕組みが整っています。
一方で、キャリア形成やライフプランの選択といった「社会的適応」の卵子凍結は、助成の対象外となっている自治体が多いのが現状です。
例外的に東京都では制度が導入され、当初は先着制でしたが、その後は対象人数を拡大する動きが見られています。
しかし神奈川県や藤沢市を含め、関東の他の自治体ではまだ制度が整っていません。
このように、目的によって利用できる助成制度に大きな差があり、地域格差が課題となっています。

卵子凍結の妊娠率は、凍結した時点での年齢と確保できた卵子の数によって大きく変わります。
医師の説明によると、34歳で20個の卵子を凍結した場合、将来的に出産に至る可能性は約90%。37歳で20個凍結すると約75%、42歳では同じ20個でも約37%にとどまると報告されています※3。若い時に確保した卵子ほど、解凍後の生存率や受精率も高いことが示されているそうです。
現在は「ガラス化凍結法」によって解凍後の卵子がダメになるリスクは大幅に減少していますが、それでも年齢が高い場合は細胞が傷みやすく、受精が難しくなるケースもあります。
国内での大規模なデータはまだ十分に揃っていないため、正確な妊娠率を示すには今後の研究が必要です。
ただし、卵子凍結は「確実に妊娠を保証するもの」ではなく、「将来の可能性を高める選択肢」として捉えることが重要です。
近年、芸能人が卵子凍結を公表したニュースが話題になることがあります。
一方で、佐藤医師は「芸能人や一部の高所得層だけの技術として捉えられてほしくない」と指摘しています。
海外ではハリウッドスターが高齢で出産するニュースが報じられることもありますが、その背景には若い時期に卵子を凍結していた可能性があります。
経済的に余裕のある人ほど利用しやすいのは事実ですが、それが格差を広げる要因になることへの懸念も示されました。
卵子凍結は本来、誰にとっても将来の可能性を広げる医療技術であり、一部の限られた層だけでなく、多くの人に現実的な選択肢として届くことが望まれています。
卵子凍結は将来の妊娠の可能性を広げる有効な選択肢ですが、必ずしも妊娠を保証するものではありません。その点を理解したうえで、自分にとって必要かどうかを判断することが大切です。
藤沢IVFクリニックでは、一人ひとりのライフプランや健康状態に合わせたカウンセリングを重視し、安全性と有効性の両立を目指した治療を行っています。
佐藤医師は「女性が社会で活躍しながら、自分の将来に備える選択肢を持てるように支援したい」と語ってくださいました。助成制度や地域格差といった課題もある中で、卵子凍結という技術がより多くの女性に届くことを願っています。
【参考文献】
※1 ※2 ※3 Goldman RH, Racowsky C, Farland LV, Munné S, Ribustello L, Fox JH. Predicting the likelihood of live birth for elective oocyte cryopreservation: a counseling tool for physicians and patients. Hum Reprod. 2017;32(4):853–859.


藤沢IVFクリニック 院長
佐藤 卓(さとう すぐる)
院長 経歴
2002年3月:岩手医科大学 医学部卒業
2002年5月:慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 入局
2006年5月:慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 助手
2010年4月:東京歯科大学市川総合病院 助教
2011年5月:慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 助教
2020年5月:医療法人財団 荻窪病院 虹クリニック 院長
資格・所属学会
日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医
日本生殖医学会 生殖医療専門医
日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医
母体保護法指定医師
日本産科婦人科学会
日本生殖医学会 (代議員)
日本人類遺伝学会
日本受精着床学会 (評議員)